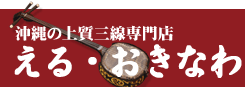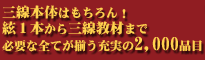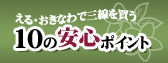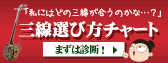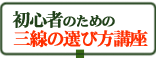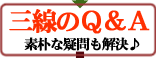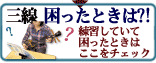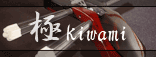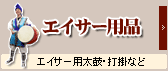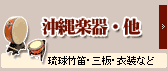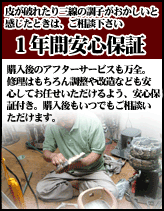|
 |
まず、糸かけをはずします。
三線の下部のお尻のところで、絃を結んでいる糸かけがあります。糸かけは胴巻きがゆるまないためのストッパーにもなっています。
糸かけがはずれにくい場合は、カラクイ(糸巻き)を回して絃をゆるめてください。 |
|
 |
胴巻きのヒモを緩めて、胴体からはずします。
(左の写真は、職人さんが棹を抜いてから胴巻きをはずしたためです。ヒモをほどけるなら、棹をはずす必要はありません)
|
|
|
※ヒモが固くてはずれない場合は、ヒモを切るか、棹を胴体から抜いて胴巻きをはずすかになります。以下、棹を胴体からはずす方法をお伝えしますが、「三線が元に戻らなくなった~!」などということがないよう、充分ご注意のうえおこなってください。 |
|
 |
棹を胴体からはずします。
※棹をはずすのは、胴巻きのヒモが固く結ばれてほどけない場合の方法です。簡単にヒモをほどける場合や、ヒモを切るなどすれば、棹と胴体をはずす必要はありません。
写真のように、職人さんは手ではずしてますが、普通は固くてはずれにくいと思うので、棹のお尻をカナヅチで叩くなどしましょう。 |
|
 |
棹を抜くところです。
棹と胴体は、はずしても後から合体できます。
※どちらが胴体の表か分かるようにしましょう。後から合体させるときに棹と噛み合わなくなります。
※三線の棹と胴体は一つ一つ形が違うため、それをうまく合体させて音が鳴るようにするためには、「ブーアティー」という職人技術が必要です。再度さおと胴体を合体させる際は、別の胴体と棹をつけたりせず、最初の組み合わせ通りにしましょう。 |
|
 |
胴巻きをはずしました。
スポッと抜けます。 |
|
 |
また棹と胴体を合体させます。胴体の裏表に注意しましょう。棹は強くはめ込んでください。
※三線の棹と胴体は一つ一つ形が違うため、それをうまく合体させて音が鳴るようにするためには、「ブーアティー」という職人技術が必要です。再度さおと胴体を合体させる際は、別の胴体と棹をつけたりせず、最初の組み合わせ通りにしましょう。
|
|